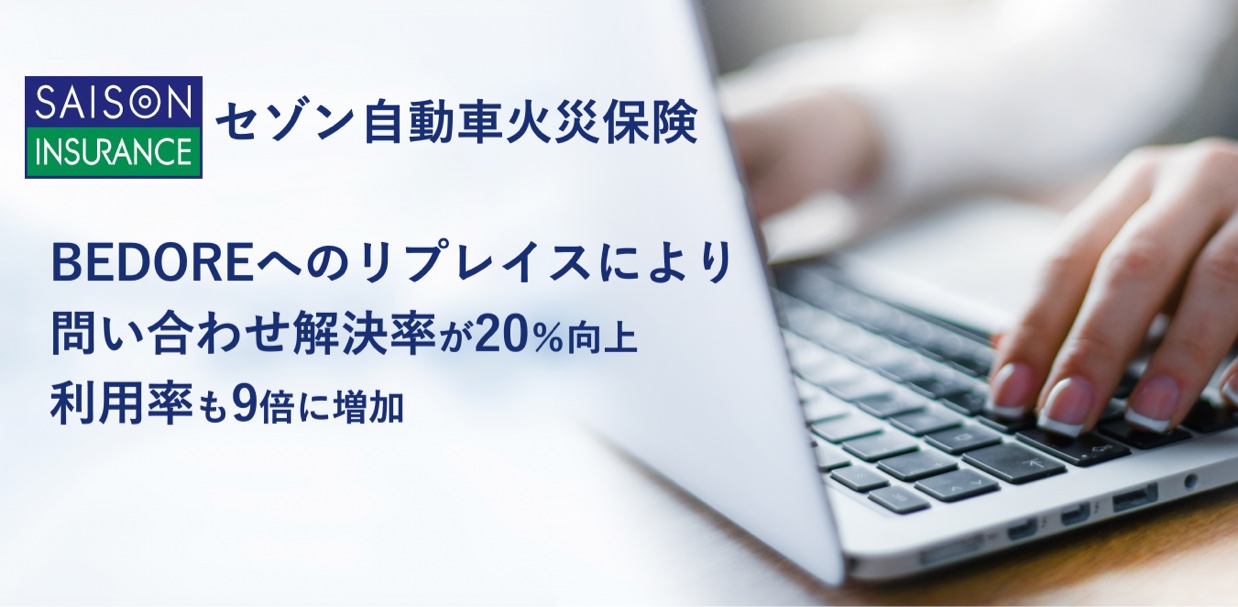
BEDOREへのリプレイスにより問い合わせ解決率が20%向上、利用率も9倍に増加
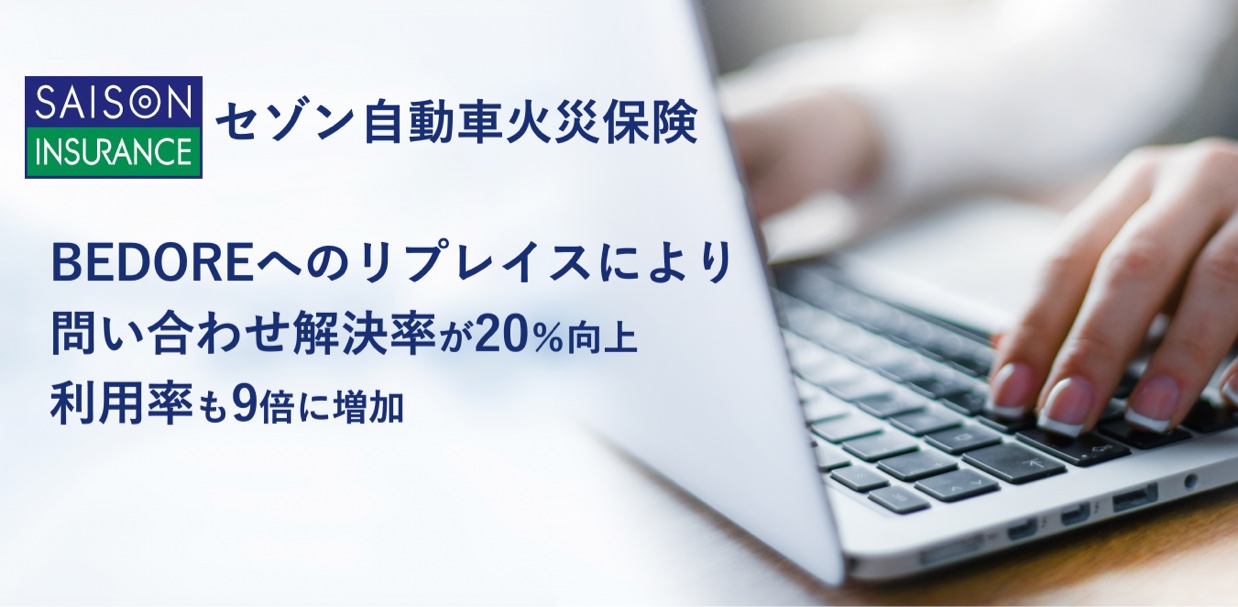
本レポートではセゾン自動車火災保険社がBEDORE Conversationへ対話エンジンをリプレイスし、解決率と利用率が大幅に上昇した事例をご紹介します
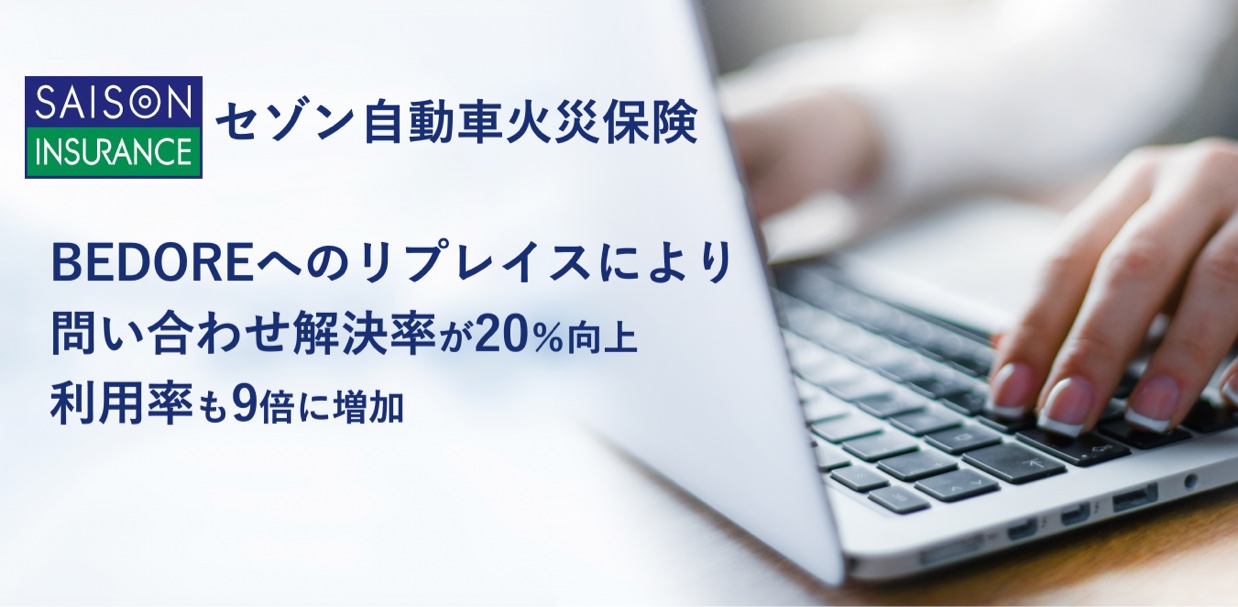
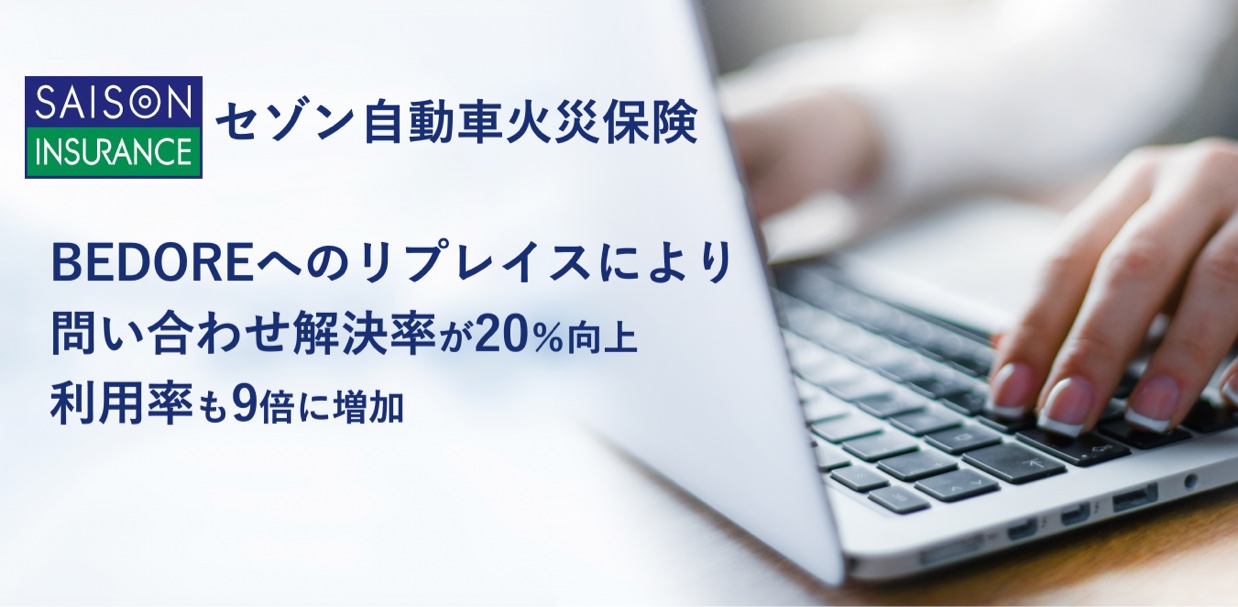
本レポートではセゾン自動車火災保険社がBEDORE Conversationへ対話エンジンをリプレイスし、解決率と利用率が大幅に上昇した事例をご紹介します
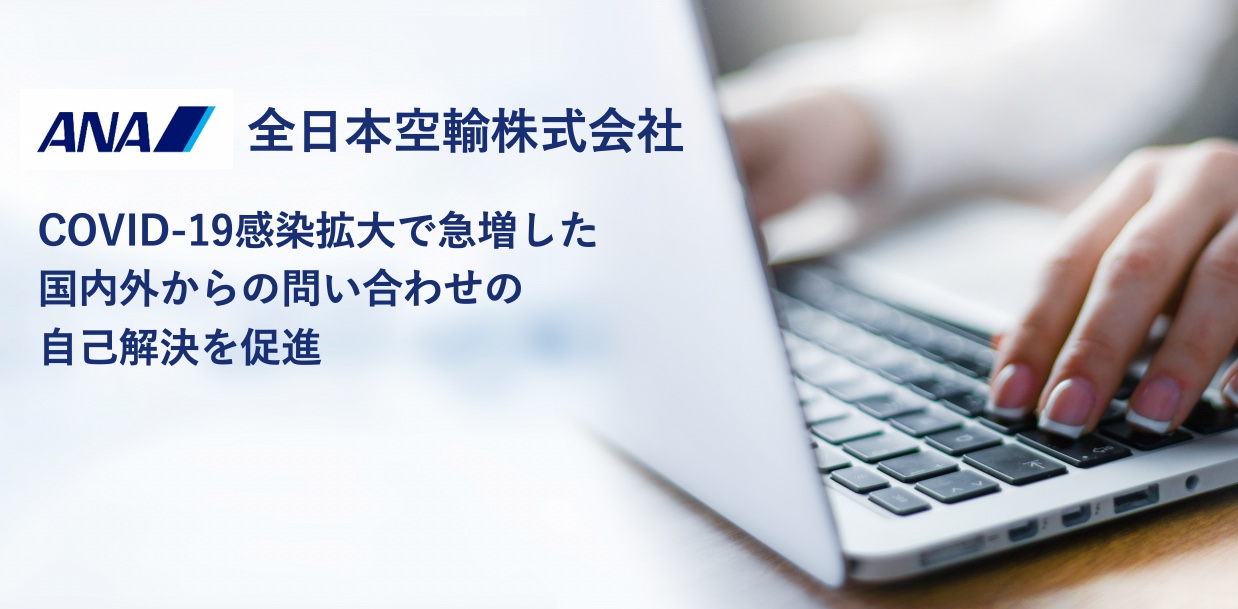
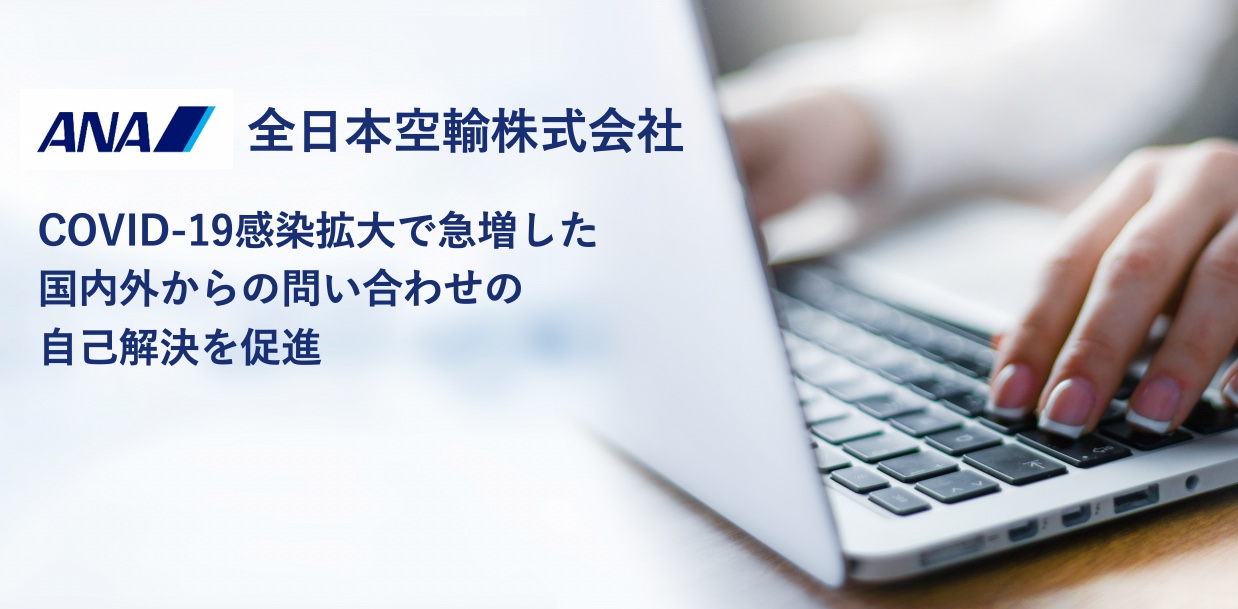
本レポートは全日本空輸社がBEDORE Conversationを活用してCOVID-19に起因する国内外からの問い合わせ急増に対応した事例をご紹介します
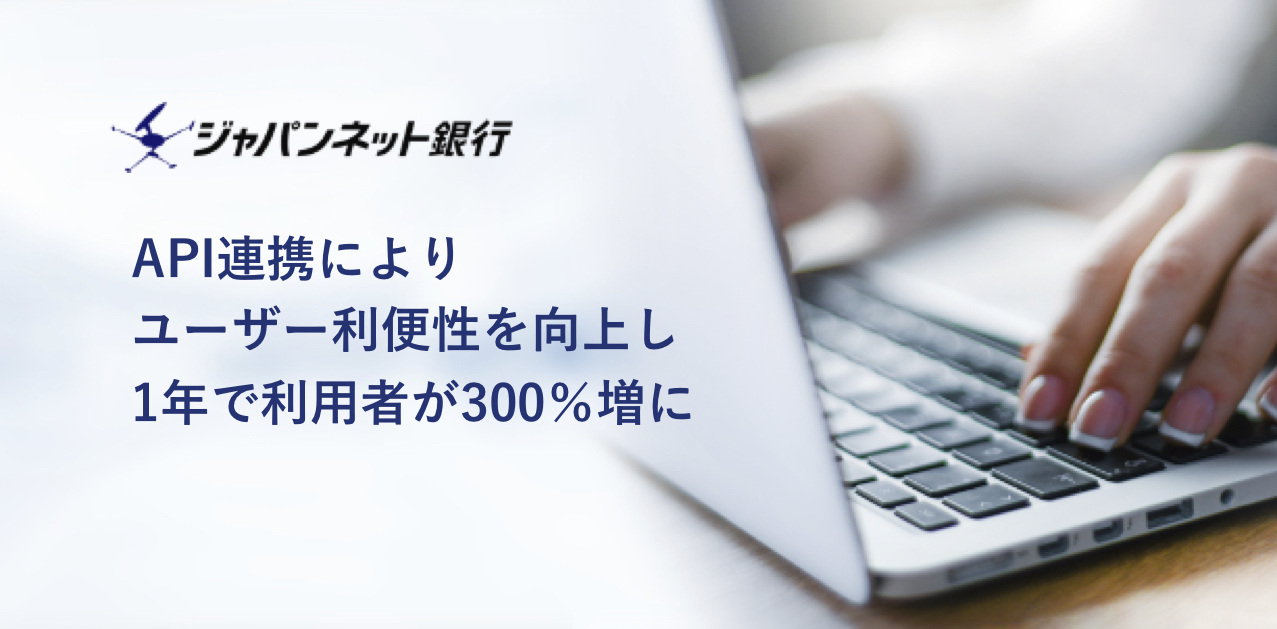
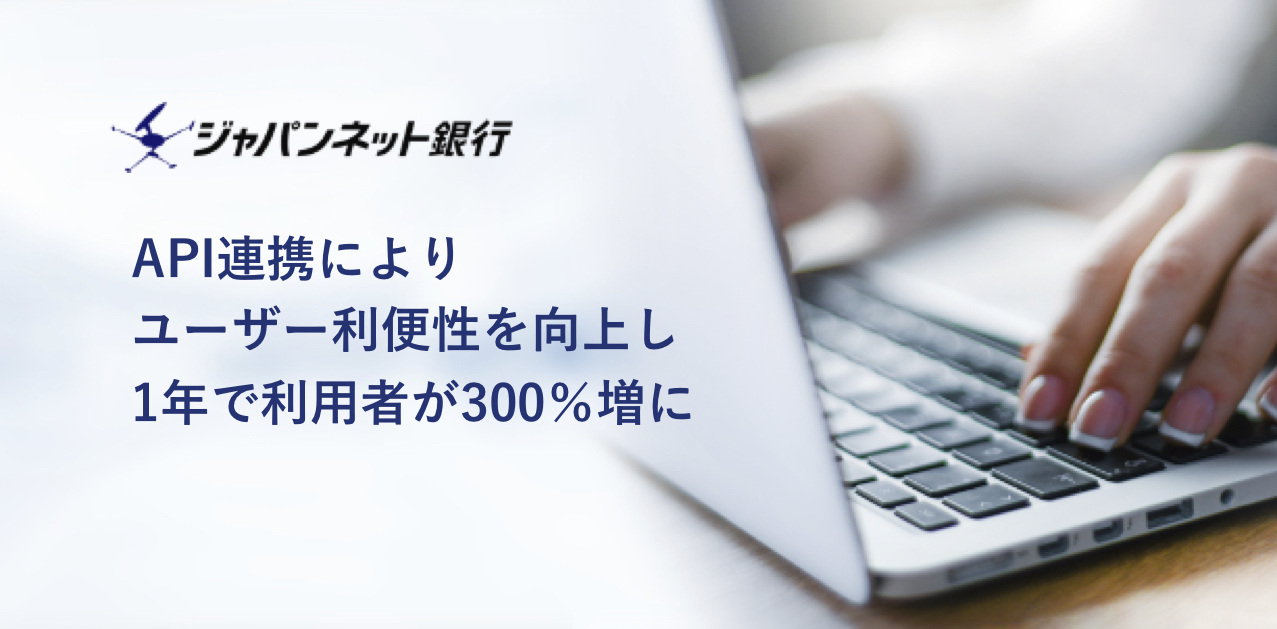
本事例はジャパンネット銀行が対話エンジンを活用し、ユーザー利便性向上やサポートの充実を実現された背景と効果をお伝えしております


株式会社バルクオム
Domestic SBU/Customer Success Division 上本 隆太氏
企業概要
〔業種〕化粧品
〔事業内容〕化粧品の企画、販売
〔導入サービス〕BEDORE Voice Conversation
〔導入目的〕定型的問い合わせの自動化、BCP対策
課題
・災害時やコロナ禍におけるコールセンターのBCP対策
・解約引き止めによるLTV向上
効果
・LTV向上に貢献しない定型的問い合わせを自動化
・オペレーターが解約希望顧客の「真のニーズ」を引き出し、契約継続に成功
・オペレーターの教育期間短縮やトークスキル向上にも貢献
―御社の事業と、ビジョンについてお教え下さい。
「世界のメンズビューティをアップデートする」というビジョンを掲げ、「Global No.1 Brandをつくる」ことをミッションに、メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」を展開しています。
化粧水、洗顔料、乳液といったフェイスケアアイテムから、ボディトリートメント、美容液マスク、ヘアケア製品まで、男性のトータルビューティをプロデュースしています。2020年5月からはテレビCMを放映し、好評を博しています。
―御社の強みやターゲット層は?
「THE BASIC MEN’S SKINCARE」をブランドコンセプトに高品質な製品づくりを強みとしています。
主なお客さまは20代~30代前半の男性が中心となっています。
―上本さんの現在のミッションは?
Domestic SBU/Customer Success Divisionのメンバーとして、業務委託先のコールセンターのマネジメント及びコール品質の向上を任されています。
このコールセンターには、購入後のお客さまから配送日の変更や解約、使い方を知りたいなどの目的でたくさんの問合せが寄せられます。入電の約7割が解約で、残りの2割ほどが配送日や配送サイクル(お届け頻度)の変更、定期コースのプラン変更といった定型的な内容です。そして残りの1割弱が肌に関する悩み相談や、商品の使い方・使用感に関するお問い合わせとなっています。
私自身は、コールセンターの運営のみならず、お客さまの購買データを分析し、LTV(ライフタイムバリュー/顧客生涯価値)を最大化することもミッションの一つとなっています。
―御社のコールセンターはどのような役割・位置づけを担っていますか。
当社ではメールマガジンや公式LINE、ECサイト、一部店頭などお客さまと様々な接点があります。その中でコールセンターはお客さまと当社のオペレーターが唯一かつ初めて直接コミュニケーションする場です。コールセンターの対応次第で当社に対するお客さまの印象は大きく変わり、お客さまのブランド体験を決定づけることになってしまいます。
これまでオンラインだけで解約を完結できる仕組みもありましたが、お客さまのご要望や解約の理由を直接お伺いするため、解約時こそオペレーターが電話でじっくりお話を聞くようにしています。そこで得られたお客さまのリアルな声を、製品開発やプロモーションにも生かしているのです。コールセンターはマーケティング活動における、CRMの重要なポジションの一つとなっています。
―どのようなコールセンターを理想としていますか。
受電までの待ち時間、声のトーン、コミュニケーションといったコールセンターにおける一つひとつの体験が、「BULK HOMME」のブランド体験としてお客さまの記憶に残ります。どのメンバーが対応しても、「家族や恋人のような親密さとあたたかさで、きめ細やかに応対する」ことを目指しています。
常にコールセンターの応対品質について改善を繰り返し、ロイヤルティを高めて、当社のより濃いファンになっていただきたいと考えています。
―こうした理想を実現する上で、コールセンターにどのような課題を抱えていましたか。
2つの大きな課題を抱えていました。1つはBCP対策です。当社のコールセンターは比較的災害の影響を受けやすい地域にあるため、台風や豪雨災害の際にオペレーターの出勤率が下がってしまうことがありました。それに加えてコロナ禍では、出社するオペレーターの数を減らさなければならない場面も多々ありました。その頃はまだ、オペレーターに在宅で対応してもらうシステムを導入できていなかったため、オペレーターの稼働不足に陥ることがありました。
もう1つは、定型業務の工数削減です。配送日や配送サイクルの変更といった定型的な対応をAIによる自動応答に任せることができれば、解約をご検討中のお客さまとじっくりコミュニケーションを取ることができると感じていました。

―BEDORE Voice Conversationを知ったきっかけは?
5年ほど前、コールセンターカンファレンスへ行った際、AIによる自動応答ソリューションについて知る機会がありました。ただ当時は当社の規模も小さく、まだ必要ないという結論でした。2020年の4月か5月、事業拡大とコロナ禍が重なって自動化が急務となったタイミングで社内の別部署からBEDOREの紹介がありました。
―BEDORE Voice Conversation を導入しようと考えた一番の決め手は?
導入コンサルタントの方が、当社の課題感をすばやく理解し、すぐ導入できるよう提案してくださったからです。当時、私自身も日々の業務に忙殺され、AIによる自動応答シナリオをゼロから設計する余裕はありませんでした。
ところが、BEDOREの導入コンサルタントは、課題のヒアリング後すぐに自動応答が可能な業務を明確化。オペレーターが人力で対応すべきケースと、AIによる自動応答が向いているケースに業務を分解し、最適なシナリオやスクリプトを提案してくださいました。
これまでの知見を生かし、当社の課題について仮説を立てて解決策を提示する提案力と、初期段階で心強い協力体制を組んでいただけたことが、導入の一番の決め手となりました。
―どのようなプロセスでAIによる自動応答を導入していきましたか。
2020年7月から自動応答をスタートしました。最初は配送サイクル(お届け頻度)の変更対応から始めて対話の精度を高めた上で、配送日や定期コースのプラン変更へと拡大していきました。
開始した当初は、お問い合わせの電話番号が様々な場所に露出していたため、配送サイクルの変更用の電話番号に、配送日や住所、定期コースプランの変更など色々な問い合せが寄せられる状態になっていました。配送サイクル変更以外のシナリオには対応していないため、当然対話完結につながらず、お客さまの要望にも答えられません。
そこで、BEDOREの導入コンサルタントは、そもそもお客さまのご要望をどう分類して整理すればちゃんと対話を完結できるようになるのかを考え、改善案を提案してくれました。具体的には、配送サイクルの変更を希望するお客さまは、「商品を早く使い切ってしまったから早く届けてほしい」か、「まだ使い切っていないので、次の商品を遅らせたい」のどちらかに分岐することを突き止め、それぞれのご要望に合った別の電話番号と対話シナリオを用意し、さらに電話に至るFAQ動線の修正まで提案してくれました。
また、AIが自動応答する項目については「FAQ」ページ上に「受付時間:24時間(言語を理解するAIが対応します)」と付記し、お客さまが混乱しないような提案もしていただけました。
その後、定期コースの変更や配送日の変更といった新しい要件にも拡大し、定型的なお問い合わせの大半は自動音声対話で対応できる状態になりました。
―導入後、どのような成果が出ましたか。
コールセンターへの入電のうち、2割を占める配送関連の問い合わせの自動応答化に成功し、しかも75%を超える高い対話完結率を達成しています。
BCP対応という観点では、人でなければ対応できないコール以外はほぼすべて自動化が達成できている状態だと言えます。
自動応答を導入する前は、オペレーターが対応するお電話のうち解約関連のお問い合わせは60%台後半でしたが、導入から約5カ月たった2020年11月現在、解約のお客様に対する対応比率は95.2%へと大幅に上昇しています。
また、オペレーターが解約のお電話に集中して対応できるようになったため、お客さまのお悩みを十分聞くことができ、結果的にお悩みが解消して継続利用につながっています。導入前から比較すると継続率は4倍に跳ね上がりました。導入前はコロナなどの影響でコールセンターがちゃんと機能していなかったという側面はありますが、それを割り引いても大きな成果です。
―他に副次的な効果はありましたか。
もともとコールセンターで対応していたお問い合わせの範囲が広く、マニュアルが何冊にもおよび、オペレーターのトレーニングもかなりの時間を要していました。しかし、Voice Conversationによって90%以上のお問い合わせが解約関連に集約されたため、まずは解約対応のトレーニングさえ行えば現場に出られるようになりました。オペレーターの教育方法が変わったのです。
継続率の改善が目覚ましいせいか、オペレーターから継続促進のための施策の提案が上がってくるようになりました。AIを導入することで、こんな影響もあるんだと気付かされました。
もっと直接的な効果だと、コールセンターが閉じている時間にも自動受付できるので、オペレーターから「自動対応のおかげで、祝休日や営業時間外でも24時間365日、配送日変更などのお客さまのご要望にお答えできるようになった」と喜ぶ声が相次いでいます。

―自動応答による業務の効率化を実現させるために、どのようなことが重要だとお感じになりましたか。
商品購入後のお客さまがどのような困りごとに直面し、何を目的にコールセンターへお問い合わせくださるのかについて知ることです。
今回、導入コンサルタントがお客さまの行動・心理を細かく分析し、コールセンターの業務を分解してくださったおかげで、自動対応の音声内容を変えたり、「FAQ」ページを細かくチューニングしたりする工夫に繋がりました。こうした深い顧客理解が、高い対話完結率に繋がったのだと思います。
日々の業務で精一杯な私たちだけでは、お客さまがどのような困りごとに直面し、本当は何を求めてコールセンターに電話をかけてくださったのか、というお客さまの「真の課題」にはたどり着けなかったと思います。
―今後の展望は。
あらゆる対応をAIによる自動応答へ移行できたら良いですね。正直、これほどAIによる自動応答の精度が高いとは思ってもみませんでした。
今後は基幹システムと連携させて、配送関連の変更受付だけでなく変更手続きも完全自動化したり、自動化範囲を広げてコールセンターの席数を減らす代わりに解約受付を24時間365日対応にするなど、AIと人の役割をうまく融合させてお客さまの満足度を高めていきたいですね。AIを使って自分たちが楽をするのではなくて、関係者みんなが幸せになれるように活用していくのが重要だと思います。
BEDORE導入事例集ダウンロード
・BEDORE導入事例のサマリー
・導入を検討したきっかけ・課題
・活用方法の実例と効果・成果



株式会社テレビショッピング研究所
カスタマーサービスセンター センター長 大須田 尚之様
企業概要
〔業種〕EC/通信販売
〔事業内容〕テレビCM・ECサイト・カタログ等を通じた健康食品・日用雑貨・家電等の販売、小売店に対する商品卸売業
〔導入サービス〕BEDORE Voice Conversation
〔導入目的〕定型的問い合わせの自動化、コールセンターの応答性向上
課題
・入電数予測が困難なコールセンターにおける応答性の維持・向上
・問い合わせ内容が多岐にわたる中での最適な人的リソース配分
効果
・人が対応した場合と同等レベルの対話完結率
・定型的問い合わせの自動化により、オペレーターを人が対応すべき問い合わせに集中
・突発的な入電数増加時でもお客様の待ち時間増加を緩和
―御社の事業と、ビジョンについてお教え下さい。
「夢のある生活提案」をビジョンに掲げ、1998年よりテレビCMを中心としたダイレクトレスポンス事業を展開しています。現在は『ダイレクトテレショップ』という通信販売ブランドで、健康食品や生活雑貨、アパレル製品などを販売しています。
近年では、「フレーバーストーン」というフライパンシリーズや、アメリカ発のノンワイヤー下着ブランド「ジニエブラ」、健康食品として累計売り上げ11億杯突破のロングセラー「青汁三昧」などの人気商品が好評を博しています。テレビCMを通じて全国により良い商品を提供し、お客さまの生活を楽しく、豊かにすることを目指しています。
―御社の強みやターゲット層は?
世界中から魅力的な商品を発掘し買い付け、いち早くお客さまに提案する購買力や、オリジナル商品の企画・開発力が大きな強みです。
地上波、BS、CS放送で放映するテレビCMによる高いリーチ力を武器に、自社ECサイト、一部商品を卸しているバラエティショップの店頭など、多数のチャネルで販売できるところも大きな特長です。ターゲット層は50~70代の方が中心。健康、美、豊かな生活に興味・関心の高い方々が多いですね。

―大須田さんの現在のミッションは?
カスタマーサービスセンターのセンター長として、購入した商品の返品・交換対応や、使い方の問合せを受け付ける75名近くの自社コールセンターを運営しています。
当社には、2種類のコールセンターがあります。新規の商品受注や問い合わせは外部のパートナー企業に委託し、300~400名体制のコールセンターで対応しています。
一方、私が担当するのは一度ご購入いただいたお客さまのリピートやアフターフォロー専門のコールセンターです。4チーム制を取り、Webサイトからの問合せ対応、インバウンド担当、アウトバウンド担当、伝票処理担当と、業務ごとに役割分担をしています。
―これまでコールセンターにどのような課題を抱えていましたか。
アフターフォロー専門のコールセンターの性質として、入電数の予測が立てたてづらく人員の配置が難しいという課題があります。受注センターであれば、テレビCMの後に購入のお電話が増える予測ができるのですが、アフターフォローの入電は必ずしもタイミングが連動しません。
さらに、入電するお問い合わせの種類も配送変更や返品・交換など定型的な問い合わせからクレーム対応まで多岐にわたるため、人員教育にも時間がかかります。最近入電が多いからすぐに人を増やして対応しよう、という柔軟な対応が難しかったのです。
―その頃、大須田さんは、どのようなコールセンターにしたいと考えていましたか。
お客さまをお待たせせず、スムーズに対応できるコールセンターが理想でした。待ち時間を減らしてすぐに受電できれば、顧客満足度も上がりますし、売り上げの維持・拡大につながります。
そこで、定型的なお問い合わせはAIで自動化し、商品の使い方や詳しいご説明など、スタッフが丁寧に説明すべきところに人的リソースを割きたいと考えていました。

―BEDORE Voice Conversationを知ったきっかけは?
2019年7月頃、チャットボットの導入を検討することになり、業界でもそのクオリティと実績に定評のあるBEDOREの方に話を聞いてみようということになりました。その際、BEDOREにVoice Conversationという自動音声対話ソリューションがあることを知りました。
定型的問い合わせはAIで自動化し、人が対応すべき問い合わせはオペレーターが対応するというコンセプトが、私が持っていた課題感にぴったりはまりました。
―これまでお客様対応の自動化を検討したことはありましたか。
3~4年前にAIのソリューションが多数登場したとき、他社のサービスを検討したことがあります。当時は展示会にも参加し、社内の導入意欲も高まったのですが、いざ要件を整理してみるとAIに求める業務があまりに増えすぎてしまったんです。金額的にもまかないきれないと判断し、そのときは導入を見送ることになりました。
BEDOREの提案は、業務に影響が出ないように小規模からスタートするという安心感のある提案でした。さらにコールセンターの予算で手軽に始められる価格も魅力でした。
―御社内にはどのように決裁を通しましたか。
テスト的に自動音声対話の対話フローを組んでいただき、役員の前でデモンストレーションを実施しました。そのときは、ヒット商品である「ジニエブラ」のサイズ交換に関する自動応答をデモンストレーションしていただきました。自動音声の質問に答えていくだけでサイズ交換が完了する様子を目の当たりにし、役員たちもとても驚いていました。
―BEDORE Voice Conversation を導入しようと考えた一番の決め手は?
AIによる高い精度の音声認識と、導入コンサルタントのみなさんによる手厚い伴走、サポートがあることがわかったからです。
それに加えて、BEDOREのみなさんが当社のカスタマーセンター業務で発生している応対内容について詳しくヒアリングしてくださった点が、特に大きな決め手となりました。どの業務を自動音声対話へ切り替えると最も効率よく工数を削減できるかを、粘り強く一緒に考えてくださり、非常に信頼できると感じました。
AIを導入すれば便利になると想像していたものの、ただテクノロジーを導入すればいいわけではないと考えています。自動音声対話に任せるべき業務を適切にピックアップし、うまく切り分ける必要があります。BEDOREの導入コンサルタントが当社のカスタマーセンター業務を知り尽くしてくださり、アドバイスをくださったおかげで、AIに任せる業務を明確化することができました。
―導入開始初期はどのような業務をVoice Conversationへ移行しましたか。
まずはノンワイヤー下着ブランド「ジニエブラ」のサイズ交換に特化し、営業時間外の自動音声対話をお願いしました。業務に影響が出ないように、まずは少量のコールで対話精度を磨き込む、というBEDOREの提案に沿って進めました。
高年齢層の多い当社のお客さま特性に合わせて、お客さまが答えやすいよう自動音声対話の質問項目を、BEDOREの導入コンサルタントにアレンジしていただきました。
Voice Conversationには自動音声対話で対応したお客さまの音声が記録されています。この録音を私たちとBEDOREのみなさんで聞き直し、お客さまの特徴的な回答や商品名の誤認、発音などをメモして、AIに認識させていきました。
例えば、サイズの中でも「XL」という単語をAIに認識させたい場合に、お客さまによっては「LL」と言うケースがあります。こうしたお客さまの言葉のゆらぎをAIに認識させる作業が重要だったと思います。
―お客様が自動音声対話を避けるといったことは起きませんでしたか。
入電時の分岐でオペレーターへつなぐ選択肢も残していますが、5割ほどが自動音声対話に流れています。対応が難しいと思われた高齢者のお客様も、あまり年齢の偏りなくお使いいただけてますね。
サイズの交換ではなく相談をしたい方や、複数のお問い合わせ内容をお持ちの方はやはりオペレーターを選んでいただいていますね。
―現在、BEDORE Voice Conversation をどのように活用していますか。
「ジニエブラ」のサイズ交換対応からスタートして対話の精度を高め、コールセンターと社内で「音声対話でも大丈夫そうだね」という雰囲気を醸成した上で、当社の主力事業である健康食品へ拡大していきました。
現在では、基幹商品である「青汁三昧」を含めた健康食品の配送日変更でも活用しています。
「ジニエブラ」については、「30日以内のお届けですか?」「送料は別途ご負担いただきますがよろしいですか?」といった注意事項の確認から、商品名、交換後の希望サイズ、氏名、住所、電話番号をお伝えいただくことで、自動的にサイズ変更が完了する仕組みを確立できました。
「青汁三昧」などの健康食品については、毎回決まった日にちにお客様へ商品が届く「定期コース」があるのですが、その配送日の変更をVoice Conversationで対応しています。BEDOREの音声認識は、日付けや住所、電話番号など数字の認識力が特に高く、安心してお任せできると感じています。
現在、「青汁三昧」などの健康食品については9時~16時を自動音声対話で対応し、16~18時で契約内容との突き合わせや確認、伝票入力などを行っています。
―導入後、どのような成果が出ましたか。
「ジニエブラ」のサイズ交換については対話完結率が75%を超え、サイズ交換を人が対応するのと遜色のないレベルで完結できています。「青汁三昧」についても安定的に完結率が70%を超えており、その他の健康食品については製品種類が多くスタートから間もないこともあり、やや「青汁三昧」を下回る完結率です。
比較的単純な応答対応をAIに任せられるようになったため、手の空いたオペレーターに他の受電対応を任せられるようになりました。また、健康食品の定期コースに関しては、問合せの8割が「配達日変更」だったため、大幅にオペレーターの工数を削減。複雑なお客さまのご要望に応対したり、丁寧に時間をかけて商品の使い方をご説明したりする時間を取れるようになったことは、大きな成果だと感じています。
―コロナ禍の影響はいかがでしたか。
2020年4月以降、コロナ禍の需要増でありがたいことに受注が急速に増えた時期がありました。しかし、商品供給網への影響で納期遅延が多発したこともあり、7月ごろはクレームが急増した時期がありました。アフターフォローのセンターの応答率が低下し、長時間お客さまをお待たせしてしまったこともありました。
お待たせする時間が長くなれば、ひとりのお客さまへの対応時間も長くなってしまいます。より一層待機時間が長くなり、お客さまの温度感が上がってしまい、オペレーターが疲弊するという負のスパイラルに陥っていました。
イレギュラーな問い合わせが急増していたため、自動音声対話がどれだけ貢献してくれたか数字で計るのは難しいのですが、応答率低下の防止につながり、お客様をお待たせする時間が減ったのは間違いないと思います。
―AIによる業務の効率化を実現させるために、どのようなことが重要だとお感じになりましたか。
自社のお客さまに寄り添い、お客さまに合わせた活用方法を考えることです。AIは優れたテクノロジーなので、導入しさえすればすぐ活用できるのではないかと思ってしまいがちです。しかし、自社のお客さまの年齢層や、パーソナリティ、受け答えの特長などを捉え、お客さまが応えやすく、AIが認識しやすい対話シナリオの設計が何よりも大切だと考えています。
実は「青汁三昧」の定期コースに自動音声対話を導入した当初、完結率があまり高くなかったんです。このときも営業時間外のテスト導入から始めたのですが、完結率が低くなった理由を分析したところ、お客さまへの質問事項が多すぎたことが判明。
配送日、箱数、商品名、住所、電話番号……と必要な項目を聞いているうちに、離脱してしまうお客さまが多かったことがわかりました。そこで、聞く項目を「配送日」に絞り、できるだけ短時間で応答を終えられるよう工夫して完結率を改善することができました。
また、青汁三昧の場合、他にも「青汁三昧 M-1」「青汁三昧 匠」と商品バリエーションがあります。こうした商品名を明確に認識してもらうよう、お客さまの応答をAIに学習させることも重要だったと感じています。
―今後の展望は。
多くの件数を占めている返品受付をVoice Conversationにお任せできたらいいなと考えています。そうすればより多くのオペレーターが受電対応できるため、より多くのお客さまのご要望に応えられるようになると考えています。

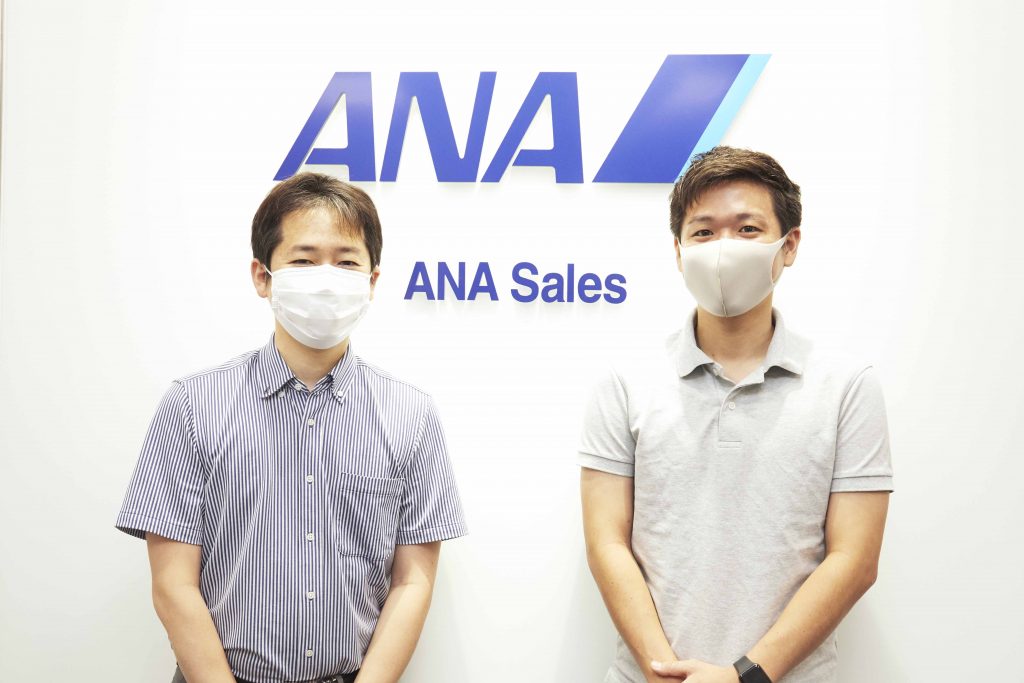
ANAセールス株式会社
旅行事業本部コミュニケーション戦略部イノベーション戦略課 マネージャー才津 亮様、加藤 梢太様
目的
・電話・メール以外のカスタマーサービス接点の獲得
・対話エンジンを含めたデジタル技術を使った新サービスの開発
課題
・災害などイレギュラー時の突発的な入電増への対応
・電話応答率の向上
・Web上でのお客様の課題解決
効果
・チャットボットで75%程度の高い自己解決率を実現し、顧客体験を向上
・コールセンター営業時間外もチャットボットで顧客サポートを実現
・Webサイトという新しい売り場で接客できる手段を獲得
―御社の業務について教えてください
才津様 ANAセールス株式会社は、ANAグループの中でマーケティング部門を担当しており、主に旅行事業と航空セールス事業の2本を柱としています。
航空セールス事業では、旅行代理店や企業・法人向けに出張などの航空券販売を行っています。旅行事業は主に旅行商品の企画と販売、特に最近ではWeb販売の割合が伸びているため、Webで予約がしやすい商品やサービスの検討に力を入れています。
―コロナ禍における御社の状況はいかがでしょうか
才津様 コロナウィルスの感染拡大により旅行の需要が低迷し、4、5月は前年対比1〜2割まで減少しました。今は「GoToトラベルキャンペーン」効果もあり、9月以降の予約は少しずつ回復基調にあります。
国内旅行に関しては、回復の兆しが見えてきました。この先冬場に向け、新型コロナウィルスの収束がどうなるかによって、また状況が変わってくるのではと考えています。
―コミュニケーション戦略部イノベーション戦略課の業務内容について教えてください
才津様 今までの旅行の形にとらわれない、新しいサービスや商品を提案することです。対話エンジンも含めた新しいコミュニケーションなど、新しい技術を使って何かできないかを日々考えています。
加藤様 私は当社の予約センターに今年の3月まで、3年間在籍していました。
予約センター在籍中にチャットによる旅行相談サービスの導入を提案し、採用されました。4月よりイノベーション戦略課のメンバーとして、プロジェクトを推進しています。

―どういった流れでチャットボットにたどり着かれましたか
才津様 今回はボトムアップで、加藤中心の予約部門の若手社員を中心とした「みらいプロジェクト」からの発信です。予約センターには若手社員が多く集まっており、その中で旧態依然とした電話中心の予約受付で良いのかと声が上がりました。
お客様に寄り添ったサービスとは何だろう?今の時代にあったサービスとは?と一生懸命考えていたようです。その中の一つがチャットで、それを実現させるために我々管理部門が動き始めました。面白い傾向だと感じています。
―当時の状況はいかがでしたか
加藤様 当時は予約センターへの電話着信数が増加していました。電話でお問い合わせいただく内容も、旅行予約に関わるご相談よりWebの操作に関わるお問い合わせの割合が多く、お客様に負担をおかけしているのがとても心苦しく感じていました。
お問い合わせいただいた中には、回答がWebサイトのFAQに掲載されているものが多くありました。お客様が画面を見て「わからないな」と思った時に、その画面から動かずに問題解決したいために電話をかけていらっしゃるのではないかという仮説がありました。このため、チャットボットのように画面上でお客様の問題を解決できれば、お客様の利便性が上がるのではないかと考えました。
―災害時の対応などはどうされていますか
加藤様 私が予約センターに所属していた2019年、甚大な被害を出した台風15号が発生し、突発的に入電数が増えることで予約センターが逼迫しました。当時はは航空便の振替手続きは電話でしかできなかったためです。
それ以外にも「台風大丈夫ですか?」とか「いつになったら航空便の振替ができますか?」など、お客様がキャンセルするかどうかの判断を決めかねてお電話されているケースも多かったのです。そうしたお問い合わせに対する状況説明や、こういうことをした方が良いですよというご案内だけなら、チャットでも対応できると思いました。
―チャットボット以外の解決策は何か試されましたか
加藤様 過去の傾向から電話着信数が多く見込まれる日や時間帯に多くのオペレーターを配置するなどの工夫はしていました。ただ、予想外に着信数が増減することも多々あり、完全に対応することは難しい状況でした。
才津様 入電数を平準化するために受付時間の延長などの施策も試みましたが、大きな成果を上げるには至りませんでした。

―チャットボットの導入までどういった流れでしたか
才津様 対話エンジンは管理部が選定しました。いくつか製品を見せていただき、色々長短を比較しました。コンタクトをとったのは2、3社と聞いています。
そして比較的早い段階でBEDOREさんに決まり、PoC(実現可能性を検証すること)はBEDORE Conversationのみで行いました。
―BEDOREを選ばれた理由はどういったところでしたか
才津様 対話エンジンを選定する上での大前提である卓越した日本語の解析能力をもつ対話エンジンはBEDORE以外にないということでした。
また、BEDOREは初期コストを抑えて導入できるところも魅力でした。本当に対話エンジンが旅行業界で使えるかはわからなかったので、スモールスタートができるのは大きいと感じました。
BEDOREは既存のWebページを改修せずに、タグマネージャーの設定、連携だけで実装できます。
導入が簡単だったので、IT部門に情報共有はしましたが、ほとんど作業の依頼などは必要ありませんでした。ユーザー部門で一括してできたのが、導入までのスピード感が出た理由なのではないかと感じています。
―導入にあたり、メンバーへはどのような説明をしましたか
加藤様 チャットボット導入前の早い段階で、システムが不慣れなメンバーに対して丁寧に説明をしました。システムに不慣れなメンバーは新しい仕組みをいれていくことに不安を感じると考えたからです。
―迅速に対応できたのは御社の社風でしょうか
才津様 ANAグループ全体に言えることかもしれませんが、新しいことに対する抵抗感が低く、経営層を含め、バックアップをしてくれるような雰囲気があります。
BEDOREのトライアルは8月、翌年4月からの運用開始で、「みらいプロジェクト」からのボトムアップがあってから半年弱でのリリースです。
BEDOREの導入にかかる費用は大きなものではありませんでしたが、経営層が新しいテクノロジーに関心が高かったため、積極的に経営層へのコミュニケーションも行いました。
加藤様 BEDORE導入を推進していた若手も経営層へデモンストレーションする場をいただくことができ、結果スピーディーな導入を実現することができました。

―導入時の体制はどのようにされていましたか
才津様 当社の予約部門のうち、チャットメンテナンスをしているチームがBEDOREの検討段階から参加しています。コールセンターの各拠点から2、3人ずつ参加してもらい、何回も会議を繰り返しました。
若手社員を中心とした「みらいプロジェクト」のメンバーの一部に加え、中堅のメンバーも入っています。若手社員のアイディアとベテラン社員の経験をうまくミックスさせながら、チャットの仕組みを作り上げていきました。
加藤様 もともと当社にあったFAQをそのまま流用せず、大幅に修正してから対話エンジンに投入しました。
予約部門にお願いして、よくある問い合わせをスプレッドシートへ入力してもらいました。そこから「この質問はよく問い合わせを受けそうだ」という質問をピックアップしてBEDOREに全部入力していきました。これは予約センターに従事してきたベテラン社員の経験がなければできませんでした。そのおかげで、BEDOREの自己解決率が高くなったと感じています。
―特別に力を入れて取り組まれたところはありますか
才津様 みんなで集まって、ワークショップのようにBEDOREのシナリオ作りをやりました。ホワイトボードに付箋を張り出して、予約の場面、決済の場面など、場面ごとに想定されるお客様お困りごとを洗い出してカテゴライズしていきました。
ワークショップは当社のコールセンターの4拠点から参加してもらって行いましたが、限られた日程の中では要素を全部出しきれず、各拠点に持ち帰って作業をしてもらいました。
加藤様 予約部門は、普段から逐一連絡を取り合って横断的に仕事をしているため、ワークショップもスムーズに進めることができました。
―ユーザーファーストの姿勢があったから最初からシナリオを作り込むことになったんですね
才津様 場面ごとに細かくFAQを出し分けています。搭乗するフライトを探したりホテルを探したりするページと、それを予約した後に名前を入れるページ、成約後に決済をするページ、それぞれでお客様が聞きたいことは違ってきます。
加藤様 予約センターではお客様から電話をいただいた時に「今どの画面にいらっしゃいますか?」と質問していたので、場面場面によってFAQが全く違うと認識していました。
才津様 場面ごとにFAQを分けておくとチャットの発生率と内容が分析できるので、Webページ自体の改善もできます。
お客様からの「わかりづらい」や「ここがいけてない」という声が数値として現れてくるので、改善検討のための材料にできます。それもあって、BEDOREのシナリオを場面ごとに細分化しました。
―BEDOREの導入コンサルタントの対応はいかがでしたか
才津様 当社はチャットボットを導入した経験がなかったので、BEDOREさんにシナリオの作り方など何から何までサポートをいただけたのでありがたかったです。BEDOREさんの事務所へ出向き、安部さんに何度も同じことを聞いたりもしました。一対一で親身に話を聞いていただけて、とてもやりやすく感じていました。
BEDORE Conversationの管理画面がわかりやすいので、一度理解してしまえば自分たちで色々な工夫ができるのも良いところだと思います。
管理画面は予約部門にも解放しており、うまくチャットボットで回答できなかった部分をメンテナンスするために予約部門にチャット部隊を作りました。普段は電話対応をしていますが、BEDOREのメンテナンスしかしない日もあります。定期的にメンテナンスをしているので、どんどん精度が上がっていると感じます。
―導入時にトラブルはありましたか
才津様 プッシュ接客発動(画面をしばらく触っていないと、対話エンジンから話しかける機能)を導入したいと、BEDOREさんにお願いしました。BEDOREさんも初めて扱う機能だったからか、タグのやりとりが何度か出戻りもありました。
そのあとで2、3画面追加したときはメール2往復ぐらいですんなりと導入できたので、最初のプッシュ接客発動のときだけはお互いに大変だったかもしれません。
BEDOREの導入でユーザー側はあまり苦労していなくて、メンテナンスにもやりづらさは特に感じなかったです。ユーザー側にITの専門知識もそれほど必要ではありませんでした。BEDOREさんに相談したらレスポンスがすぐに返ってくるので、気持ちよく進められました。
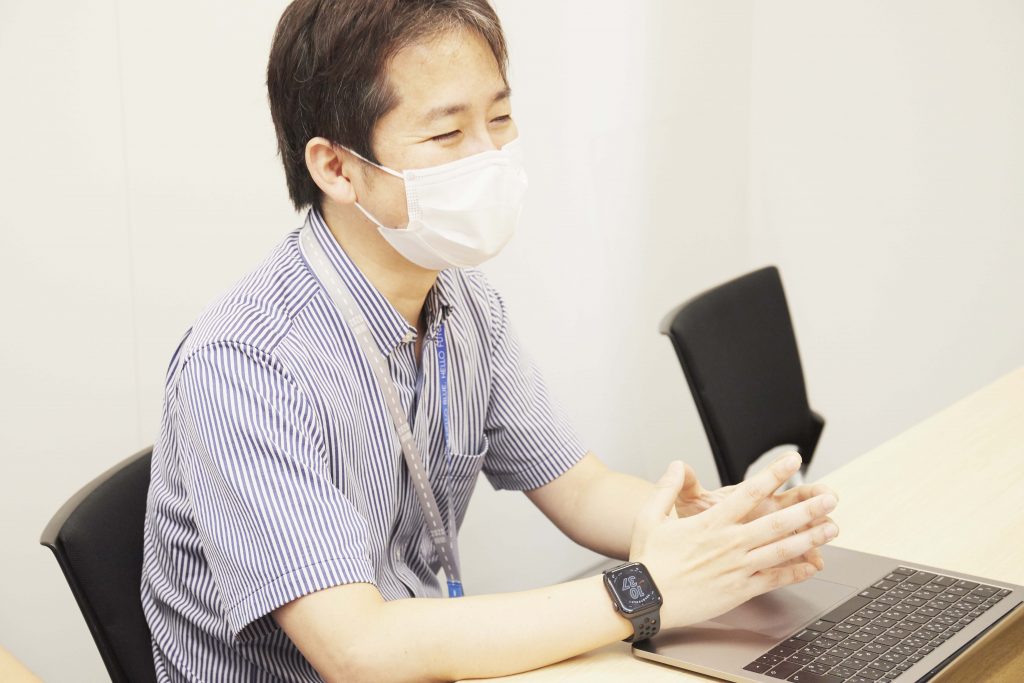
―BEDOREを実際に使ってみていかがでしょうか
才津様 比較したものが少ないので一概には言えませんが、BEDOREは導入当初からかなり高い自己解決率が出ていました。全てのシナリオを用意していないのにこれだけ高い数字が出るということは、それなりに精度が高いのではと感じました。
―BEDORE導入後予約センターの状況はいかがでしょうか
才津様 当社の予約センターの営業時間は9時から18時です。そして営業時間外のチャットボット利用率が高くなっています。もしチャットボットがなければ離脱して他社を利用していたかもしれません。数値化は難しいですが。
加藤様 私が持っていたデータによると、チャットボット利用が多いのは夜20時から22時で、平日の20時から21時は非常に多いです。
才津様 ざっくりですが、電話予約の営業時間と営業時間外のチャットボット利用率は5対5くらいではないだろうかと認識しています。
―実際のご利用数の遷移はいかがですか
才津様 BEDOREは小ボリュームで少額のプランがあるので、最初はトライアルでスモールスタートしました。ですがリリース初月で予想を上回る利用があり、想定の倍どころではない数の利用があったため、プランをアップグレードしました。
BEDOREをお客様に使っていただけないと、導入した意味がありません。その後もますますチャットが定着してきているので、利用件数は右肩上がりです。
―冒頭でも話のあった災害時対応などはいかがでしょうか
加藤様 台風などのイレギュラーな状況では、関連する質問をプッシュでお客様に提示したら分かりやすいのではと考えました。プッシュでチャット画面を表示させ、初期画面に「台風のことでお困りですか?」と表示させる対応をBEDOREさんに提案したところ、3~4日で対応してくれました。
災害時に電話が逼迫した状況は変わりませんでしたが、私の肌感では操作方法などのお問い合わせは減り、航空便の振り替え手続きなど、優先して対応したい内容の問い合わせが増えました。定型的な問い合わせはチャットボットが解決し、人が対応すべき問い合わせにもっと時間が割けるようになったと感じています。
それまでコールセンターでは、台風による電話の逼迫状況に対応できないことがオペレーターの心理的なストレスになっていました。BEDOREのチャットボットが導入されて対応できることが増えたので、安心してお客様に対応できるようになりました。
才津様 台風が来た時に「現場で頑張って」ではなく、社内全体で協力できるようになったと思います。
実際に台風災害が発生した際、BEDOREのチャットボットで台風関連のFAQがかなりの数発動していました。チャットボットがその場でお客様の疑問に回答できていなかったら、そのうちの何割かのお客様はコールセンターにお電話されていたかもしれません。
―BEDORE導入後、どの様な効果がありましたか
加藤様 お客様からのメール問い合わせ数は7〜8割くらいに減少しています。
チャットはリアルタイムで返答できますが、メールは2、3日以内に返信するとアナウンスしています。そのためメール返信が遅いとお客様からご連絡頂くこともありましたが、そういったことも少しずつ減少してきていると感じています。本当に急ぎのお客様は、チャットで解決しているのかもしれません。
才津様 BEDOREとともに有人チャットも導入したので、そちらへお客様が流れている可能性もあります。
加藤様 Webサイトの操作説明を求めるチャット内容が多いので、そのあたりの用件の電話は減っているのではという肌感があります。あとは「領収書が出せない」など、BEDORE導入前に「この問い合わせ多いよね」と感じていた用件がかなり減りました。
才津様 チャット回答の一部には、WebサイトのFAQに飛ばしているものがあります。ある程度まではチャットで回答してから詳しくはFAQでと誘導しているので、結果的にFAQが見られた回数は増えているかもしれません。
―BEDORE Conversationの精度はいかがでしょうか
加藤様 BEDOREの導入前に予約センターで設定した自己解決率※のKPIは、65%から75%です。BEDOREは導入当初から75%を超えていて、すごいなと思いました。
※チャットボット対話後に表示される「お役に立ちましたか?」というアンケートに「はい」と回答された率
才津様 おそらく正答率(BEDOREとして正しい答えを出せている可能性)はそれよりも高いと思われます。正答であっても、お客様がご納得いただける内容ばかりではないので、自己解決率はそれよりも落ちて70%強くらいです。実際の正答率は肌感で80%強くらいではないでしょうか。
―NGチャットの処理※はどう対応されていますか
※チャットボット対話後のアンケートに「いいえ」と回答されたチャットログを再学習して精度を高める処理
加藤様 月に2回くらいは、NGチャットをこちらで振り分けています。これは本当に間違っていると判断すれば修正をかけているので、その都度BEDOREの精度は上がっているのではと感じます。
こちらのチャットではちゃんと答えているが、お客様の希望が当社ではできないことだとNGチャットになることがあります。たとえば、当社では領収書の但し書きを3つから選んでいただくのですが、お客様は航空券と宿泊代を分けて欲しい、でもセットの商品なのでできかねますと回答すると、ご納得いただけなくてNGになってしまいます。
才津様 BEDOREの導入当初からそうですが、お客様はチャットの答えが正しいかではなく、不満を感じて「いいえ」を押すことがある。これは仕方がないと思います。
―その他に副次的な効果はありましたか
才津様 BEDORE導入によってFAQが整備されたこと、若手社員発案のチャットプロジェクトが部署全体を巻き込んで成功したことです。改めて、お客様視点でどういうことができるかを考える良い経験になりました。
加藤様 チャットボットの導入効果について半信半疑だった予約センターのメンバーが今は「こうやってシナリオをすればお客様によりわかりやくなるのでは」と自ら提案するようになっています。今まで以上にお客様視点でサービスを考えることができるようになったと思います。

―御社ならではの意識されたことはありますか
才津様 当社はお客様満足度に関しては元々品質面で評価いただけていて、応答部門は旅行部門で満足度第1位をいただいています。BEDOREを活用し、よりカスタマーサービスを向上させていければと考えています。
加藤様 当社はお客様から聞かれたことに答えるだけで終わるのではなく、それでは画面を見ながら一緒に操作しましょうとか、画面のここを見ていただけますかなど、寄り添う言葉をかけるようにしています。
一方で、お客様がわかるまで解決しようとすると電話の応答時間は長くなり、積滞化してしまう矛盾も抱えています。BEDOREのチャットを導入したことで、改善できるのかなと感じていることろです。
―今後のBEDOREの展開についてはいかがでしょうか
才津様 私たちの夢として、対話型のエンジンを作りたいと考えています。ここにBEDOREさんの優れた言語解析技術を使えないだろうかと。
あたかもお客様が旅行カウンターへ行き、そこで会話をして予約するような感じでお客様の要望を聞き出し、最後に旅行工程の組み合わせ商品を提示します。チャットボットでの対応が実現する前の段階として、有人チャットで実現できないか検討しています。
加藤様 このアイディアは、NGチャットからきています。NGチャットを分析していると「沖縄の旅行のおすすめを教えて」など提案やおすすめを求めるお問い合わせが一定数存在することに気が付きました。こうしたチャットボットのログがプロジェクトのヒントになっています。
才津様 当社は日本全国に支社と支店があるため、各地の従業員がよく訪れるお店ですとか、従業員がぜひ行ってほしいとおすすめする場所などをデータとして集めることができます。こうした情報を元に、お客様が対話エンジンに旅行の相談をできるサービスを実現したいと考えています。
そういったマイスターサービスと、シンプルに用件に回答するチャットとを併用できればと考えています。
―御社における今後のデジタル化戦略など展望はありますか
才津様 社内での問い合わせにも、対話エンジンを利用してはどうかと考えています。新しい働き方として、テレワークを推進していくなかで、社内問い合わせの効率化はすぐに効果が出るでしょう。
―最後に、AI技術の発展に期待する未来について教えてください
才津様 お客様に対して1to1で色々な提案がインターネットでできたらいいなと思います。そこにぜひ、AIの力を使いたいと。先ほど話した対話型エンジンのマイスターサービスもその一つで、実現のための準備は着々と進めています。
また、AIと人が協働してお客様をサポートできるようになると良いですね。旅行カウンターのプロのようなAIがあって、その隣には私もいるというような。AIと一緒に、お客様がより安心して旅行を楽しんでいただけるようなカスタマーサービスを提供できたらと多います。
自社だけではなく他社さんとも連携していく中で、CE(カスタマイズエクスペリエンス)戦略と、DXとをうまく絡めて顧客体験の向上を図っていきたいと思っています。


損害保険ジャパン株式会社
カスタマーコミュニケーション企画部 鈴木様、小林様
秋田カスタマーセンター兼自動車保険チャットボット担当 大門様
荻窪カスタマーセンター室 近藤様、上原様、アリヤ様
目的
・時代の変化に合わせ、電話以外の問い合わせ手段を増やす
・AIなどの最新技術を活用してお客さまの期待に応えたい
課題
・カスタマーセンターの営業時間外にお客さま対応ができない
・電話が苦手なお客さまへのサポートチャネルが不足していた
・以前利用していた対話エンジンはメンテナンスが大変で利用率も低かった
効果
・カスタマーセンターへの問い合わせ数が半減し、有人チャットへの接続数も減少した
・簡単なやりとりで済む用件が減り、オペレーターがお客さまのサポートに集中できるようになった
・対話エンジン運用というオペレーターの活躍の場が増えてモチベーションが上がった
―御社の業務について教えて下さい
鈴木様 損保ジャパンは、代理店ビジネスモデルで損害保険事業を行っている会社です。いわゆるダイレクト通販型と違い、お客さまの身近に代理店が存在し、ご契約の締結からメンテナンスまでのきめ細かいフォローをしています。
―カスタマーコミュニケーション企画部はどのような部署ですか
鈴木様 カスタマーコミュニケーション部門全体の企画立案と運営を行っています。
企画グループでは全国に5つあるカスタマーセンターのよりよい運営のための各種施策の検討・実施を行っており、その中でデジタル技術の活用も検討しています。また、カスタマーセンターに集まる多くのお客さまのお声からの気づきをもとに、商品やサービスを作る本社の関連部署に提言もしています。
―カスタマーセンター室はどのような部署ですか
鈴木様 実際にお客さま対応をしている部署で、全国で5つのカスタマーセンターがあります。
アリヤ様 荻窪カスタマーセンター室は、インターネットで保険加入されるお客さまの対応を中心とした業務を行っています。
―御社が目指すカスタマーサポートのあるべき姿とはどういったものでしょうか
大門様 保険会社のカスタマーセンターに電話をする機会は、一生のうち何度もあることではありません。もしかしたら、お客さまにとっては長い人生のうちで2、3回、もしくはたった1回の可能性もあります。
たとえば勤め先に保険関係の書類を提出することや、大きな災害が起きて自分は大丈夫だろうかと心配することなどがないと、保険会社に問い合わせる機会はなかなかないでしょう。
お客さまのもしもの時にいつも安心を提供する、その特別な1回のお問い合わせの際にお客さまとしっかりと向き合い、ベストな対応をすることを目指しています。
―チャット型対話エンジン導入前のご状況はいかがでしたか
アリヤ様 荻窪カスタマーセンター室では、インターネットで加入する海外旅行保険を担当しています。以前はインターネットからどう契約すればよいかわからない、高齢の方などは契約したくても自分ではできないというお問い合わせが多かったように思います。
鈴木様 カスタマーセンターは24時間365日営業しているわけではありません。平日は9時から20時、土日は9時から17時が基本的な営業時間です。
海外旅行保険のお手続きサイトのアクセス数がもっとも多いのは22時頃です。カスタマーセンターは営業時間外ですから、お客さまの疑問や不明点にすぐ答えられるような環境が整っていませんでした。
―導入前に感じていた時代の変化や課題感などはいかがでしょうか
鈴木様 当社の公式Webサイトには「よくあるご質問」を掲載していますが、年々閲覧数が伸びています。お客さまは疑問の答えをまずはWebへ求めに行っているようで、電話よりもWeb環境の利用が増えていると感じています。
大門様 当社のカスタマーコミュニケーションにおけるゴールは、顧客体験価値の向上と考えています。
お客さま求めるライフスタイルに応じて、お客さまの好きなタイミングに、好きなツールを使って問い合わせができるようにしたい、中でもデジタル技術を活用して、お客さまにより寄り添った対応ができないかと感じていました。

―BEDORE Conversation導入前は別のテキスト型対話エンジンをお使いだったそうですね
鈴木様 2015年ごろの対話エンジンの黎明期に、BEDOREではない対話エンジンを導入しました。「問い合わせ」手段としての機能よりも「親しみやすさ」を重視し、お客さまに愛着を持っていただけるようにキャラクター設定をするなど、ブランディング的な要素と気軽に親しみをもって「よくある質問」を検索いただきたいという目的意識が強かったです。
大門様 その対話エンジンはキーワードマッチング型に拠るところが多く、お客さまの実際の入力履歴をみながら細かく1つ1つキーワード等を設定していくメンテナンスにも負荷がかかっていました。例えば、ひらがなと漢字、読み替え語句なども設定する必要があり、なかなか運用・改善のサイクルを起動に乗せることができない状況だったと記憶しています。
また、お客さまの利用状況の確認やキーワード設定等も管理サイトなどで私たち自身だけでは対応が完結せず、外注する必要がありました。
小林様 利用数も伸び悩み、1か月あたり2,000件程度のリクエストに留まっていました。なお、BEDOREは1か月間で6万7,000件ほどのリクエスト数、となっており、利用数も大幅に伸びました。
鈴木様 メンテナンスは1人で1日7時間やって、200件程度こなせます。例えば1,000件を作業するとなると、とても1人では手に負えません。
この対話エンジンのメンテナンス負荷に対する利用数の少なさ、一方でお客さまがサポートをWebに求める傾向が年々強まるという環境変化を踏まえて、よりお客さまのニーズに答えられる環境を構築したいという考えに至りました。
―新しい対話エンジンに求めたものはどんなものでしょうか
鈴木様 以前の経験を踏まえ、全国5拠点にあるカスタマーセンターで実際に日々電話でお客さま対応を行っているメンバーが主体となってメンテナンスなどの運用を軌道に乗せられるように、キーワードマッチング型ではなく自然言語処理能力が高いもの、かつ、管理サイトが使いやすいことを重視しました。
小林様 対話エンジンの性能面での選定基準は、お客さまからの問い合わせに対する正答率が高い、つまりお客さまが求めている答えを案内できるかどうかです。
お客さまが対話エンジンに問い合わせても解決しない場合は、有人チャットへ接続してご案内することも想定していたのでその連携が効率的にできるかどうかも、ポイントにしていました。
―BEDOREの導入決定までの流れを教えて下さい
小林様 対話エンジンは6社検討しました。
鈴木様 製品化されているものもあれば、研究所の実験段階のものもありました。対話エンジンで本当にお客さまのお問い合わせに答えられるのか、対話エンジンの再検討を行うのは今のタイミングが最適なのか、それとも先の技術進歩を待ったほうがよいのかなど種々の懸念がありました。
まずはPoC(実現可能性を検証すること)を前提として、2018年の5月から新しい対話エンジンの検討を始めました。当社には「デジタル戦略部」というデジタル技術の活用を支援する専門部署があり、本件も選定にあたっての支援をしてもらいました。多角的に評価をした結果、その年の秋口にBEDOREさんでPoCを実施することを決定しました。
PoCは翌年1月に実施し、その後社内稟議等を経て本格導入を決定しました。2020年の1月末に、保険商品の改定に合わせ海外旅行保険にてBEDOREをリリースしました。
―対話エンジンの選定プロセスで大変だったことはありますか
小林様 PoCでは完全な状態で対話エンジンを準備できないことから、実際にお客さまには触れていただかずに実際に日々電話でお客さま対応を行っているメンバーでお客さまに代わってBEDOREの検証を行いました。なので、お客さまに本当にこの対話エンジンを使っていただけるのだろうかと、不安に思うこともありました。
近藤様 実際にカスタマーセンターで対応したお客さまからの問い合わせ内容を入力して検証するなど、検証方法を工夫しました。
鈴木様 実際には、対話エンジンに完全な質問で入力しないお客さまもいらっしゃいます。チャットのログを見た時に、私たち企画部門のメンバーではお客さまが何を聞きたかったのかがわからないケースもあります。
普段、カスタマーセンターでお電話で応対する際はお客さまの完全ではない質問に対し、「こういうことですか?それともああいうことですか?」と聞き返しをすることでご要件を絞っていきます。でもその最適な聞き返しの方法を企画部門のメンバーはわかっていません。そういった点で制約条件のあるPoCにおいて、実際に日々電話でお客さま対応を行っているメンバーに検証してもらうことは重要なポイントだったと思います。

―BEDOREを使ってみてどのようなメリットを感じたでしょうか
鈴木様 BEDOREに感じるメリットは自然言語で処理できて、かつ管理サイトが使いやすいことです。その2つのバランスが取れているのがBEDOREさんで、他社と比較するととても良くできていると感じます。
管理サイト上で運用サイドでだけで完結できる機能が多く、一部の管理者向けシステム設定で複雑な点はありますが、メンバーが日々利用する機能の大半はマニュアルを読み込まずに感覚的に使えることもメリットだと感じます。
小林様 PoCでのBEDOREの正答率は想定を超える数字でした。機械学習を実施する前の数値にもかかわらず、他社と比較しても非常に精度が高いと感じました。
さらに、導入決定後もリリースまでの準備が多岐に渡るのではないかと懸念がありましたが、BEDOREさんの導入コンサルタントの方にとても丁寧かつ親身に対応していただけ、実際の準備は非常にスムースに進みました。
―BEDORE導入後の業務内容に変化はありましたか
上原様 荻窪カスタマーセンターではBEDOREの日々のメンテナンスに加え、営業時間、有人チャットへの接続等各種設定を行っています。BEDORE関連のメイン業務はチャットボットの応対履歴を確認してのAI学習で、他の拠点も同様です。
たとえば「コロナ」など、あるキーワードの入力数が急に増加することがあります。そういった事象をチャットボットの応対履歴を確認する際に把握した場合は、今後BEDOREでお客さまにスムースに回答することができるよう、すぐにBEDOREへ反映させることを心がけています。
大門様 今年9月頭に台風12号が来た次の日には、急遽台風の被害に遭われたお客さまにスムースに各種案内ができるようBEDOREにインテント(FAQ)を作りました。
普段はインテント(FAQ)投入に社内の申請などで1か月ほどかかりますが、それを待っていられないと判断し、スピーディに対応をしました。最近ではBEDOREでの急増ワードをもとに、BEDOREに表示させる選択肢を入れ替えてよりお客さまが目的のご質問にたどり着きやすくなるよう工夫することもあります。
―BEDORE導入コンサルタントのフォローはいかがでしたか
鈴木様 BEDOREの導入コンサルタントの近藤さんは実はコールーセンターのご出身で、企画部門の人間だけでは対話エンジンの設定はしきれないと、最初に教えて下さいました。そのアドバイスがなければ、企画部門の私たちだけで頑張ってリリースも運用もしようと考えてしまったかもしれません。
そのアドバイスを踏まえ、近藤さんとともに実際に日々電話でお客さま対応を行っているカスタマーセンターのメンバーを中心にしてBEDOREを構築していきました。カスタマーセンターのメンバーも、コールセンターの事情に詳しくて、かつては同じ立場だった近藤さんに支援していただいたことでとても安心感があったと思います。
上原様 実際に日々電話でお客さま対応を行っているカスタマーセンターで対話エンジンの構築やメンテナンスをするのが初めてだったので、何をすればいいかとか、どれくらいのスケジュールで進めていいかが全くわからなかったのです。
BEDOREさんに相談したらすぐに駆けつけてくれ、インテント(FAQ)の当社で必要な申請期間や商品のリニューアルのタイミングなど、当社の細かい事情も加味したスケジュールを作ってくださいました。
わかりづらい、使いにくいことがあればなんでも言ってくださいとサポートして頂き、とても安心して構築・メンテナンスすることができました。
小林様 こちらからの幾度もの質問・要望に対していつも迅速かつ丁寧に対応していただき、かつコールセンターの事情からシステム構築面と知見も広く、BEDOREさんの導入コンサルタントの方の人材面に関しても大変満足しております。
鈴木様 BEDOREさんは製品のアップデートが早く、他社さんの対話エンジンにある機能など「あったらいいな」と思っていたものが導入企業の要望をもとに「製品」として反映されていく点もいいなと思います。導入各社の要望に合わせてその企業だけ「カスタマイズ」するのではなく、BEDOREさんの「製品としてアップデートしていく」方向性は、導入企業の各知見を集約して早く導入企業全体に還元するよい方法だと感じています。
例えば、BEDOREのウィンドウについて、必要のないお客さまには「閉じる」選択肢をBEDOREのシステムで実装したいとお願いしたら、製品のアップデートでBEDOREの構築期間中に実現されました。アップデート前までは個々のWebページ側で各種のシステム設定をしないと実現できなかった機能が、対話エンジンの設定だけで叶うのが便利だなと感じます。

―BEDOREを導入したことによる効果についてお聞かせください
小林様 BEDOREのリクエスト数は2020年8月の1ヶ月間で約6万7千と、非常に多くのアクセスがありました。
アリヤ様 BEDOREの導入以前、お客さま対応はカスタマーセンターの営業時間内でしかできませんでしたが、今は24時間365日いつでもBEDOREで対応できます。
インターネット契約が基本の海外旅行保険は20時以降、21時や22時などのカスタマーセンターの営業時間外の契約が多いです。その時間帯でお客さま対応ができるようになったのは、本当によかったなと思います。なかなかお電話をかけるお時間が取れないお客さまに対しても、BEDOREで気軽に問い合わせをしていただけるようになりました。
大門様 BEDOREから有人チャットに接続するケースが減っていまして、1月は2,427件あったのに対し2月は1,329件まで減少しました。
鈴木様 BEDOREの導入でお客さまのアクセス手段が増え、有人チャットの総コンタクト数はBEDOREの精度向上までは一時的に増えるのではないかと懸念していたところもあります。仮に減っても2割くらいではないかと。
リリースから2週間後くらいから有人チャットが減った実感があり、結果的に有人チャットでのお問い合わせが半減しました。ここまでは想像ができなかったので、とてもびっくりしました。
近藤様 逆に、有人チャットでのお問い合わせ1件あたりの対応時間は増えています。以前はお客さまと2、3回のやりとりで終わることが多かったのが、10回程度やりとりをしないと応対が完了しないケースが増えたと感じます。
鈴木様 当社のカスタマーセンターが目指しているのは、デジタル活用で人間が対応することとデジタルで対応することの最適化を図っていくことです。
10回程度のやりとりを必要とするお客さまは、アドバイスが欲しいなど人による対応やより強い安心感を求めているのではないでしょうか。そう考えると、すべてを対話エンジンだけで対応すべきではないのかもしれません。
対話エンジンでより早く、気軽に問い合わせたいというニーズに対応し、有人チャットや電話では安心感を提供する。その両方に対応できるのが当社のカスタマーセンターのよさだと感じています。
―コロナ禍においてBEDOREをどのように活用いただけましたか
アリヤ様 私の担当する海外旅行保険では2020年1月以降、コロナウィルスについてのお問い合わせが急増しています。そのため、BEDOREに表示させる選択肢にコロナウィルス関連のコンテンツを追加して対応しました。
現在海外旅行保険関連のお問い合わせのうち約8割はコロナウィルス関連となっていますが、ほぼBEDOREの対話エンジンで対応が完結している印象です。
小林様 コロナウィルスだけでなく今後突発的な外的要因で急激にお問い合わせ数が増え、お電話での応対が万が一間に合わなくなるような事態にも、BEDOREの対話エンジンが同様に活用できればお客さまにいつもどおりに安心をお届けできると感じました。
―BEDOREを導入したことによる副次的な効果はありましたか
近藤様 対話エンジンは、有人チャットとは違い実際のお客さまの応対履歴を元にBEDORE自体を学習させていく作業が必要です。その作業を通して、お客さまがどのような質問をされたのかなどをデータとして見ることができます。
小林様 BEDOREが正しい回答を返しているのに、お客さまが「役に立たなかった」と評価されるケースもこともあります。つまり、お客さまが当社のサービスや商品に対して満足されていないということです。その気づきを、サービスや商品の改善に活かしたいと考えています。
大門様 カスタマーセンターの現場からは、対話エンジンが導入されたらオペレーターが必要なくなるのでは、という懸念がありました。ですが、実際にはBEDORE導入後は対話エンジンの育成もカスタマーセンターの現場の業務に加わり、対話エンジンをどう育成し、活用するかなど、新しい活躍の場ができました。
今までオペレーターは電話を受けることがメイン業務でしたが、デジタルを活用した別の活躍機会ができたことで、モチベーションが上がっています。さらにはBEDOREのメンテナンス等の結果が正答率の向上等として目に見えるので、わかりやすさもあるようです。

―BEDOREで今後やりたいことはありますか
近藤様 実際のBEDOREの応対履歴を元に新しいインテント(FAQ)の追加を検討するのですが、例えば自動車保険等はお客さまのアクセス件数が多いために検討すべき課題が多岐に渡っていて、優先順位付け、絞り込みに苦労しています。その絞り込み作業等が自動でできないかを、BEDOREさんと取り組み中です。
上原様 今BEDOREの対話エンジンに入っているのは自動車保険、自賠責保険、火災保険、特約火災保険、海外旅行保険です。今後も対象の商品を増やしていくことでお客さまのニーズに応えていきたいと考えています。
―AIの発展について期待されることはありますか
アリヤ様 さらなる顧客体験の向上につながることを期待しています。BEDOREの対話エンジンの導入で、お客さまはいつでもお問い合わせができるようになりました。
近年、日常お客さまが利用されているコミュニケーション手段の変化から電話でのコミュニケーションが苦手な方も増加していると聞いています。そういったお客さまにも気軽に、対話エンジンを使っていつも「安心」がご提供できるといいなと思います。
一方、今後も人でしかお客さまに寄り添えないことや人ならではの安心感などはあると思っています。今後もデジタルの便利さに、人による感動・信頼の融合を目指して最適な組み合わせを模索していきたいと考えています。
小林様 対話エンジンの話からは少し離れますが、引き続き人にしかできないこととして残る電話応対においては、お客さまとの応対をシステムに記録しています。その応対を記録することに時間を要しているので、将来的にはAIを活用して短縮できないか検討していきたいです。結果として、人ならではの高い安心感や信頼感のご提供に注力していけたらと考えています。
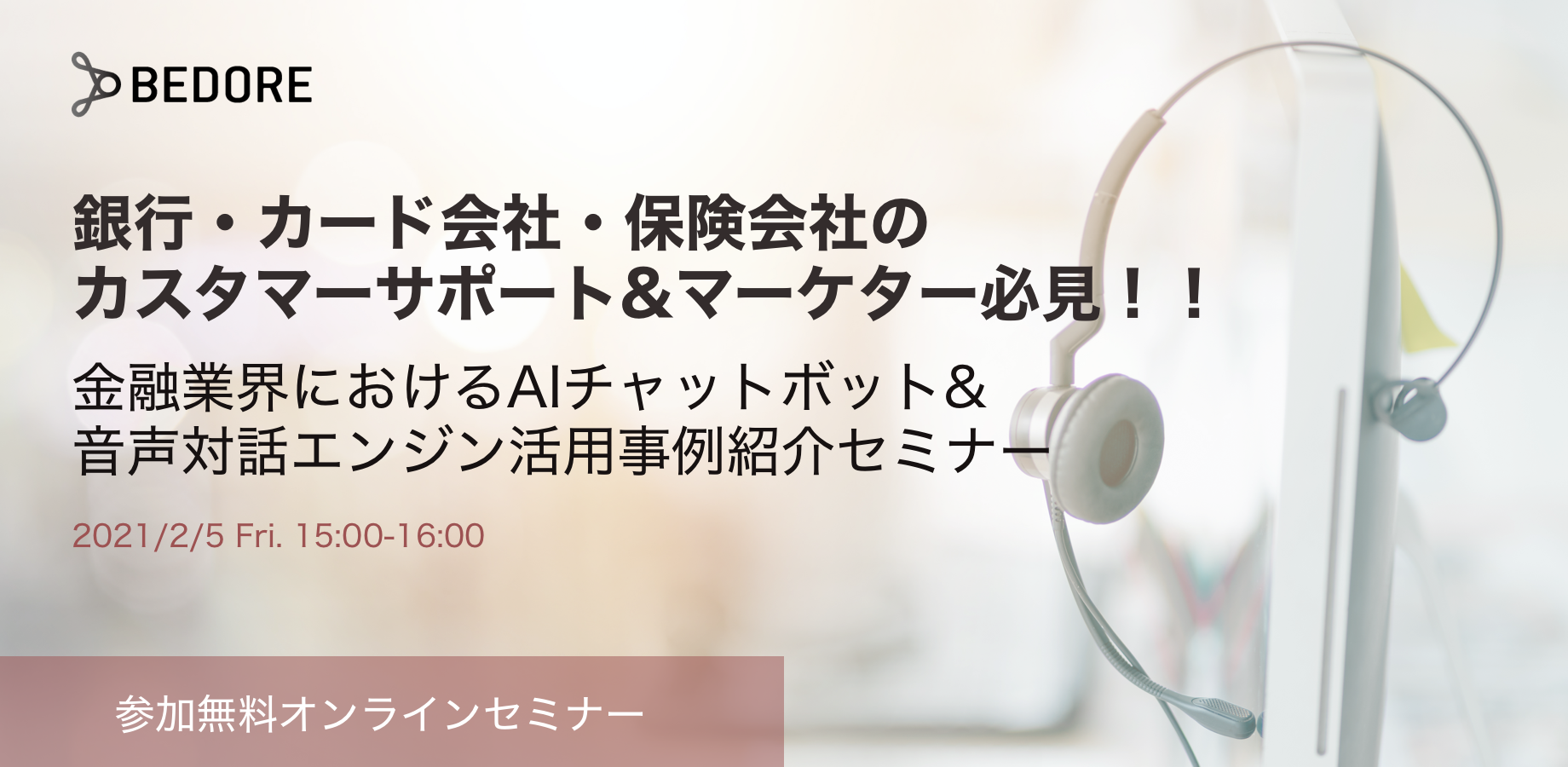
金融業界のカスタマーサポート、マーケターの方必見のオンラインセミナーを開催いたします。